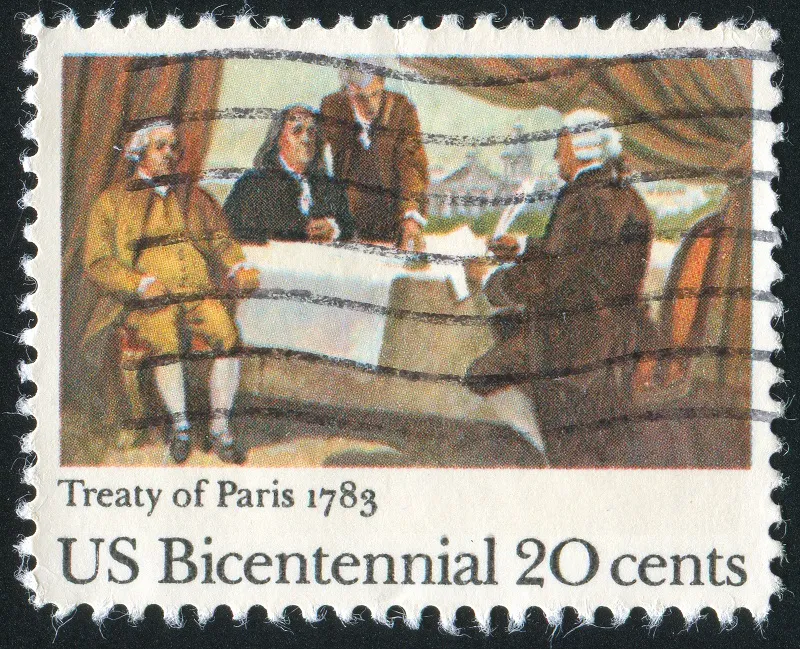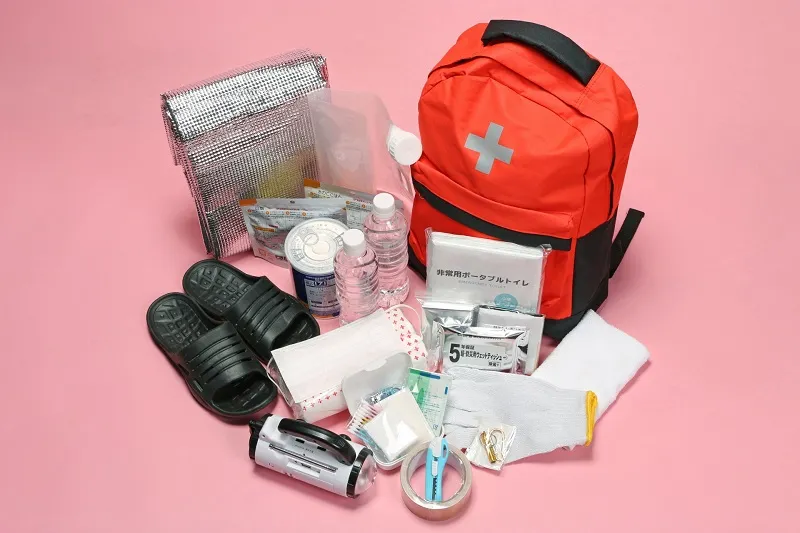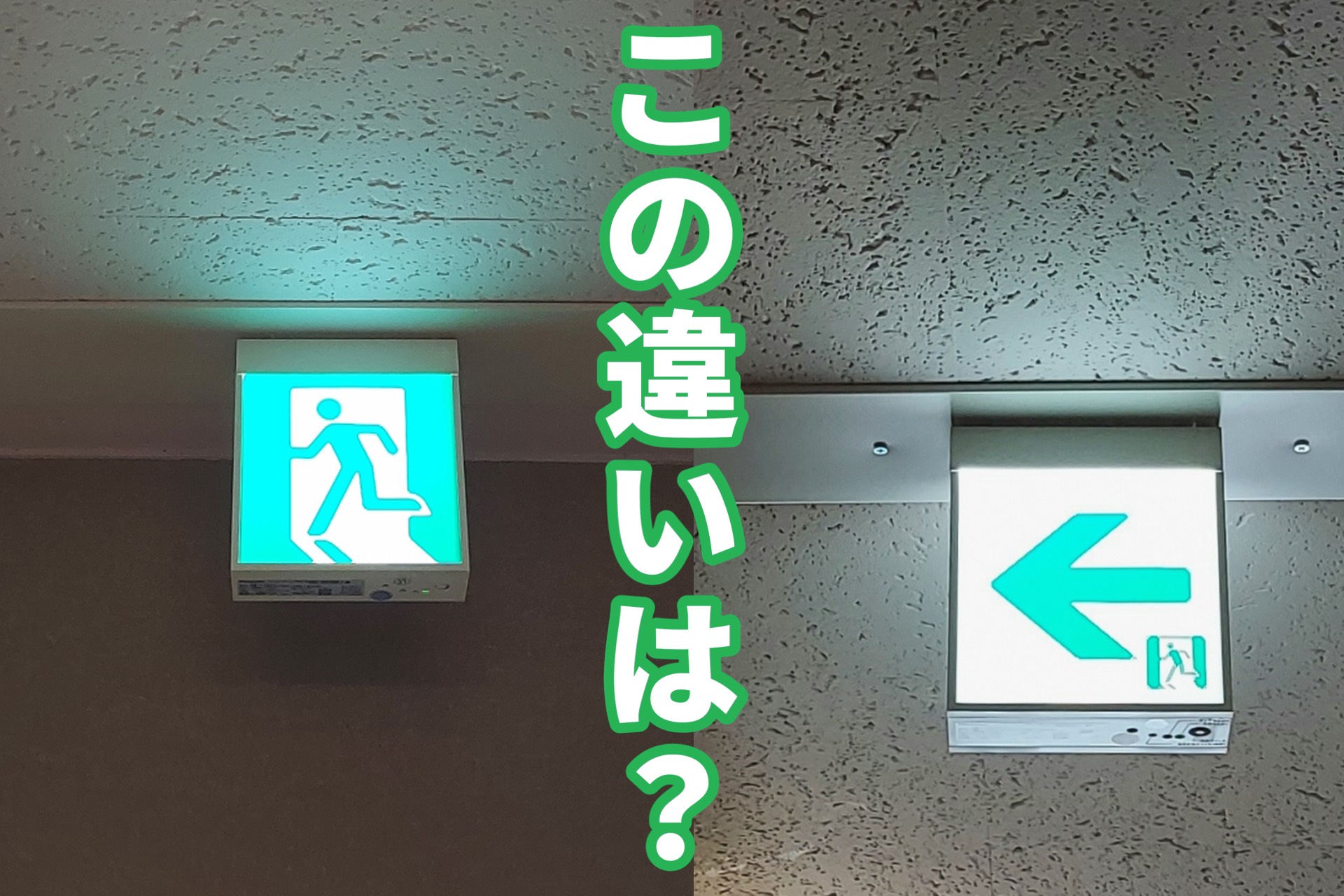「被り物の服」は不便?「前開きの服」絶対主義者の意見

オフィスワークでは社内の設定温度が、人によっては暑かったり、寒かったりします。
最先端技術の空調設備でも、皆が快適な環境を作るのは難しいかもしれません。
私は体温調整能力が低いので、一枚羽織ったり、脱いだりして調整しています。
それがしやすいように常に前開きの服を着ているのですが、以前から思っていたことがあります。


被り物の衣類がなぜ存在するのか
主に「スウェット」「セーター」「プルオーバー」等についてですが、「被り物」以外の「前開き」の衣類は
「カーディガン」
「ブルゾン」(アウター(上着)に使われる名称ですが)
「シャツ」(〇〇シャツと言わない場合は、スーツのインナーのような襟付きのもの)
案外「羽織(はおり)」と呼ぶ人が一番多いかもしれません。
前開きor被り物で名称があまり変わらない傾向がありますね。
英語では「pullover」が被り物に該当しますが、前開きの英単語は無さそうです。

着脱しやすい服のは大前提
体温調整のために着脱する人にとっては着脱しやすいのは大前提です。
春夏秋は上着の着脱で済むかもしれませんが、冬は室内で上着を脱ぐのは普通として、室内が暑くて脱ぎたい時、この「被り物」が立ちはだかります。
髪型や化粧が崩れかねないという理由で「脱ぎたくない」という場面があるのではないでしょうか。
ショップの試着室でもわざわざ「被り物(服)を脱ぐ為の被り物(帽子)」が置いてありますし。
そうでなくても物理的に大きく動く必要があって、狭い場所で着脱しづらかったりします。

全部の洋服が前開きだったら・・・
何が言いたいかというと
「そもそも肌着(Tシャツ)の上に着る物は全て前開きだったらよかったのに」
ということです。
一昔前にこんな言葉がありました。
「おしゃれは我慢」
私には意味がわかりません。
特にセーターと呼ばれていた編み物、主にウールの物は、暑くても脱ぎづらいし肌に触れないわけでもないのに、洗いづらい。
今は自宅で気軽に洗えるものもあるかもしれませんが、なぜこれが一般的に浸透したのか謎です。
実際のところは、ファッションの多様性だと思いますが。
すぐ思いつくものだと、前開きではないことで、Tシャツでよくある「プリント」のデザインがスウェットでも見られますね。
スウェットは逆にプリントがないと何のデザインもないのペーっとしたものになってしまいます。
メンズでは無地のTシャツ=ほぼ下着でしたし。
ファストファッション時代ではそうでもないですが。

前開きにする事で中心に線が入る事の影響
前開きにする事で中心に線が入る事の影響を考えてみました。
コートでよく見られるステンカラー(比翼仕立て)は、前開きの留め具を目立たなくするという意図がありましたが、実際「目立たなくする」効果しかありません。
例えば被り物のインナーを主役にした、丸みがかったバルーンシルエットのような「中心線のない」イメージを「前開き」で表現するのは難しそうです。
個性を表現するには利便性を捨てる必要性を否定できません。
なので普段着としては利便性を重視するべきかなと思いました。
被り物は不便なので普段着には向かない。
なんて考える人はいないでしょうが、私はそう思いました。

まとめ
ところで、「快適」で「見栄えが良く」「似合う」服を簡単に選べたらいいですね。
私は大手ファストファッションブランドの服が好きですが、ネット購入で済ませたくても、「見せ方が上手すぎて現実味がない」ので試着したくなります。
お店も商品を魅力的に見せたいのは当然だし、仕方ないことです。
売る側も買う側も公平な判断基準としては、
- 「生地のアップの写真を掲載する」
- 「寸法を持っている服と比べる」
- 「それを元にした判断力」
判断力とかいうとハードル高そうですが、それが現実ですね。
売る側はありのままを魅力的に見せる技術をつけて、買う側もネットでのお買い物スキルを身につける。
それが現代のネットショッピングに必要な事だと思います。