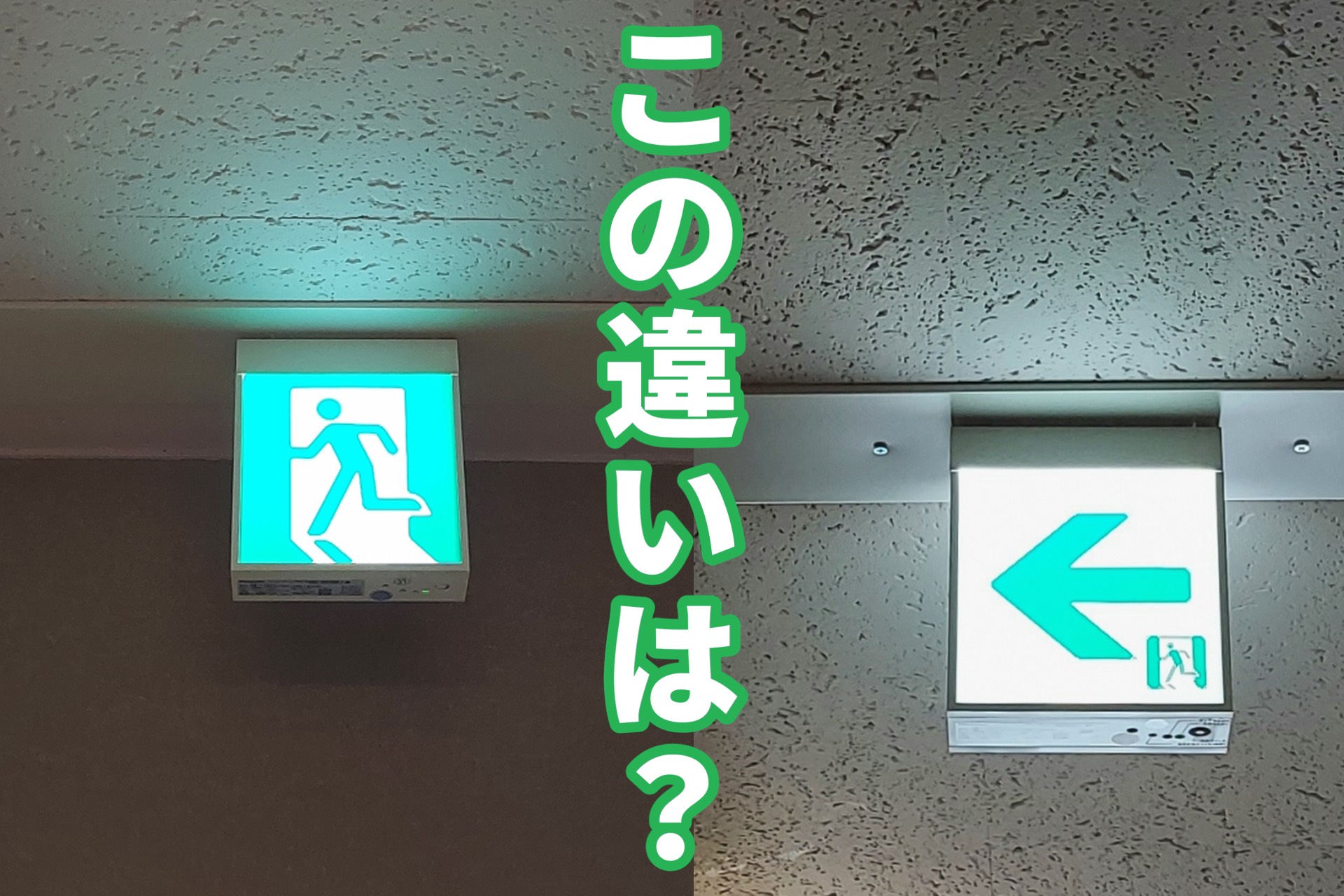おうちでも簡単に取り入れよう!おいしく健康的な身体づくりを目指す薬膳とは?

みなさんは薬膳、と聞いてどんなイメージが思い浮かびますか?
ひょっとすると名前はよく聞くけどいまいちどういうものかよくわからない想像しにくい部分もあるかもしれません。
筆者の思い浮かべるイメージも、健康にいいけどおいしくなさそう、漢方が入っていそう、聞きなれない食材を使うのでちょっと難しそう……などなど、少しハードルの高いもののように思えてしまいます。
そもそも薬膳とはどういうものなのか? どういう食事なのか? と思われている方も多いのではないのでしょうか。
薬膳とはいったい何なのか!その基本について調べてみました。

薬膳とは
薬膳とは、東洋医学の中医学の考え方に基づいて考案された食事のことで、食材と生薬を組み合わせた料理をいいます。
栄養や効果、おいしさや見た目などのすべてのバランスがそろった食養生の方法で、病気になる前に体調不良を改善し、健康的な体作りを促すことを目的としています。
食養生とは病気の予防・治療、健康保持、体質改善などを目的とし、その人の体質や体調に合った栄養バランスのいい食事になるように調整することをいいます。
西洋医学が病気の患部に着目して診断し、薬を用いて早く治すことを目指しますが、一方中医学とは身体全体のバランスや患者の体質を診て、普段の生活の中から病気にかからないよう予防をしていきます。
また、身体の不調が症状として表れることを「病気」と呼びますが、明らかな症状が出ていなくても、身体のバランスが崩れている状態のことを「未病」といい、この「未病」を中医学の考え方をもとに、その日の自分の状態に応じた食材を摂ることで、症状を改善します。また精神安定や美容促進の効果があります。
薬膳には様々な基本的な考え方があります。
この考え方を理解しながら薬膳を取り入れることでよりおいしく健康的な身体づくりに繋がっていきます。
薬膳の代表的な考え方について紹介します。

薬膳の基本的な考え方
1.陰と陽
ひとつめの考え方は『陰陽』です。
地球上にあるすべてのものは「陰」と「陽」に分けられるという考え方であり、例えば太陽(陽)と月(陰)、昼(陽)と夜(陰)、男性(陽)と女性(陰)といったかたちで、陰と陽がバランスをとりながら存在をとりながら世界の調和が成り立っていると考えられています。
その考え方をそのまま食材に当てはめると、「陰」の食材は主にカラダを冷やす作用のある食材、「陽」の食材は体を温める食材、となります。
それぞれ体調や季節に合わせて陰と陽の食材を選んでいくのは勿論、健康を保つにはどちらかに偏り過ぎてしまうのも不調の原因になってしまいます。
陰に偏ると体が冷えて重くなり、逆に陽に傾くと肌が乾燥したり吹き出物ができやすくなります。
そのためバランスよく摂っていくことが大事なのです。
- :陰の食材例
- 牛肉、鶏肉、鮭、えび、かぼちゃ、たまねぎ、ねぎ、にんにく、しょうが、桃、みかん、紅茶、シナモン、くるみなど
- :陽の食材例
- 豚肉、たこ、かに、あさり、なす、トマト、ごぼう、しいたけ、バナナ、柿、いちご、緑茶、投入、そば、のりなど
2.五臓
五臓とは人間の身体の「肝・心・脾・肺・腎」を指し、身体の部位のことを示しています。
ですが、西洋医学における臓器とは違った考え方をするため、いわゆる「臓器」と同じ役割をするわけではありません。
たとえば「肝」は肝臓という意味ではなく、自律神経の調節や血を貯めておく臓器のことを指します。
- 肝
- 自律神経や情緒をコントロールし、血液を循環させて蓄える器官。そのほかにも目の機能や関節の動きなどもつかさどる。
- 心
- 心は精神や意識をつかさどり調節する器官。血液を身体全体に循環させる役割を持ち、冷えから身体を守り、精神状態を安定させる役割を持ち、身体の臓腑にも影響を与える。
- 脾
- 胃や腸などの消化器官を指す。食事の消化吸収を調節し、食材の九州や分解、栄養を身体全体に行き渡らせる役割を持つ。
- 肺
- 呼吸や全身の気をコントロールする器官。呼吸の免疫機能の調節、水分の調節や肌の保護など、身体に潤いを与え広い範囲に影響を与える役割を持つ。
- 腎
- ひとの成長や発育、代謝などを調節する器官。尿の分泌と排出をつかさどり、発育の促進や老化現象の防止、ホルモンバランスの調整、エネルギー蓄積などの役割を持つ。

3.五行
五行については聞いたことがある方もいるのではないでしょうか。
こちらもまた薬膳における重要な概念の一つで、宇宙の万物は性質の異なる5つの物質で構成され、それぞれが相互に作用したり反発しあったりして成り立っていることをいいます。
その5つの性質が「木・火・土・金・水」の五行で、自然界にある物質は五行のいずれに分類することが出来ます。
4.五味(六味)
五味とは基本となる5種類の味を意味する、「五行」と深く紐づく考え方で、酸味、苦味、甘味、鹹味(塩味)、辛味の5つで、味によって身体に異なる効果をもたらします。
食材が五臓に対して作用する効能そのものも意味するため、単なる「味(味覚)」とは違った概念になります。
昨今ではこの五つに「淡味」を加えて「六味」とするのが一般的となってきています。
今回は「淡味」含めた六味にて紹介します。
酸味(すっぱい味):
- 作用…下痢や汗、咳を止める。緊張を和らげる。血液をきれいにする解毒作用がある。肝臓や目にいいとされる。
- 働き…「肝」の働きを促進。→消化を助ける
- 食材…烏梅、レモン、ざくろ、酢、ブルーベリー、りんご、スモモなど
- 五行…木
苦味(苦い味):
- 作用…解熱作用。体の熱や水分を除去し調節。心臓や小腸にいいとされる。
- 働き…「心」の働きを促進。→血液を全身に送り出す。
- 食材…セロリ、緑茶、アロエなど
- 五行…火
甘味(甘い味):
- 作用…食欲増進。けいれんの改善。筋肉の緊張を緩めたり血を補ったりする。滋養強壮の効果がある。胃や口にいいとされる。
- 働き…「脾」の働きを促進。→消化不良、不要物の排出。
- 食材…そば、牛乳、卵、トウモロコシ、穀類、トマト、ブドウ、キュウリなど
- 五行…土
辛味(辛い味):
- 作用…血の巡りを活発にし、機能を促進。身体を温める作用がある。発汗作用。鼻や肺、大腸に良いとされる。
- 働き…「肺」の動きを促進。→呼吸、全身の水分調節。
- 食材…ネギ、ショウガ、ワサビ、ニンニク、唐辛子、コショウなど
- 五行…金
鹹味(塩み):
- 作用…しこりを柔らかくする。便秘や腫物を改善。
- 働き…「腎」の働きを促進。→水分の代謝と貯蔵。
- 食材…イカ、アサリ、タコ、味噌、昆布、海苔など
- 五行…水
淡味:(薄い味):
- 作用…身体の潤いを助ける。体力を保持しながら利尿する。
- 働き…「脾」「五臓」の動きを促進。→水分バランスの調節。
- 食材…冬瓜、はと麦、トウモロコシのひげ、湯葉、白菜など

5.五気
五気とは食材が持つ5つの性質である「寒性・涼性・平性・温性・熱性」をいい、例を挙げると冬に温かい食べ物を食べたときに身体が温まってきたり、暑い夏にキュウリや冷えたスイカを食べると身体がひんやりとするといった、すべての食べ物に対して身体を冷やしたり温めたりする性質のことをいいます。
食材を食べたあとに身体にどのような影響があるかで分類されています。
寒性:
- 体を冷やす作用がある。鎮静作用や消炎作用があり、のぼせやすい人や高血圧の人が積極的に摂ると良いとされるもの。
- 例→カニ、ゴーヤ、スイカ、トマト、ゴーヤ、バナナ、塩、寒天など
涼性:
- 寒性よりは作用が弱いものの、体を冷やす作用がある食べ物。寒性と同じように鎮静作用や消炎作用がある。
- 例→豚肉、そば、ナス、セロリ、キュウリ、水菜、豆腐など
平性:
- 身体を温めたり冷やしたりするなどの作用がなく偏りの少ない食べ物。すべてのタイプの人に良いとされる。
- 例→鶏肉、豆類、白菜、キャベツ、ニンジンなど
- 温性:
- 熱性ほどではないが、体を温める作用がある。興奮作用があり、冷え性の人が摂るとよいもの。
- 例→牛肉、ショウガ、栗、シソ、ニラ、みかん、タマネギ、鮭など
- 熱性:
- 温性よりさらに身体を温める作用が強い食べ物。温と同様に興奮作用があり、冷え性の人に加えて貧血も摂ると良いとされる。
- 例→羊肉、唐辛子、ニンニク、コショウ、シナモン、酒類など

これらの考え方を組み合わせながら、自分の健康状態に合わせて実践していくのが薬膳になります。
「なんとなく」の不調にも対応できる幅の広さが薬膳の長所でもあります。
クコの実やなつめ、スパイスのような独特の風味のある食材だけではなく、いつものスーパーで購入できる食材でも気軽に薬膳料理にチャレンジすることが出来ます。
薬膳と普通の料理との違いは、薬膳はおいしさを楽しんだりエネルギーを摂取するための食事ともまた食材の持つ性質を見極めながら、バランスよく組み合わせて作ることで日常生活をより良いものにするためにサポートしていくものになります。
寒さも厳しく何かと体調を崩しやすいこの時期だからこそ、少しずつ日々の食事に薬膳を取り入れてみてはいかがでしょうか。
この記事を書いた人
『イートラスト株式会社 CS・テクニカルチーム 課長/ B-rise運営事務局 副局長』
飲食業界で現場・SV・マーケティングを経験し、2014年イートラスト株式会社へ入社。ディレクター業務・カスタマーサポート業務を経て、現在はSEOやホームページ運用全般を請け負う「テクニカルチーム」を立ち上げ、責任者を担う。飲食業界に携わっていたこともあり、サービス業様へのWebマーケティング・SEO/MEOで貢献していくため、日々新しい試みを模索している最中です。