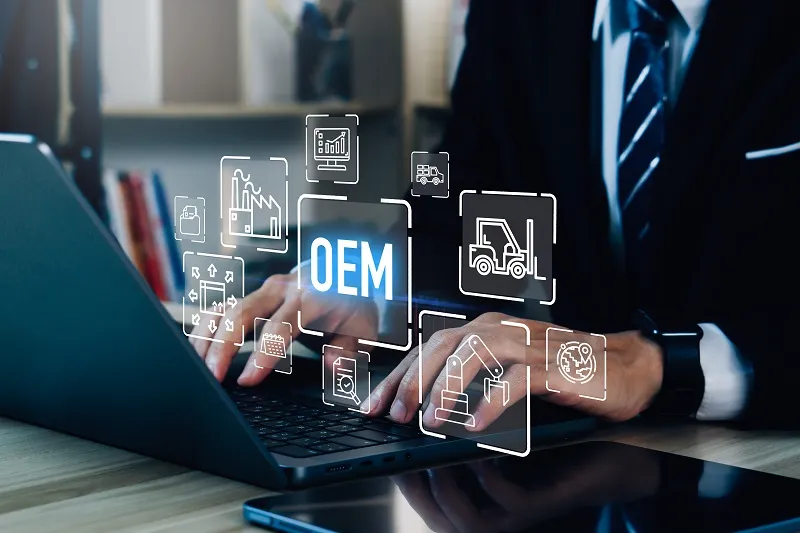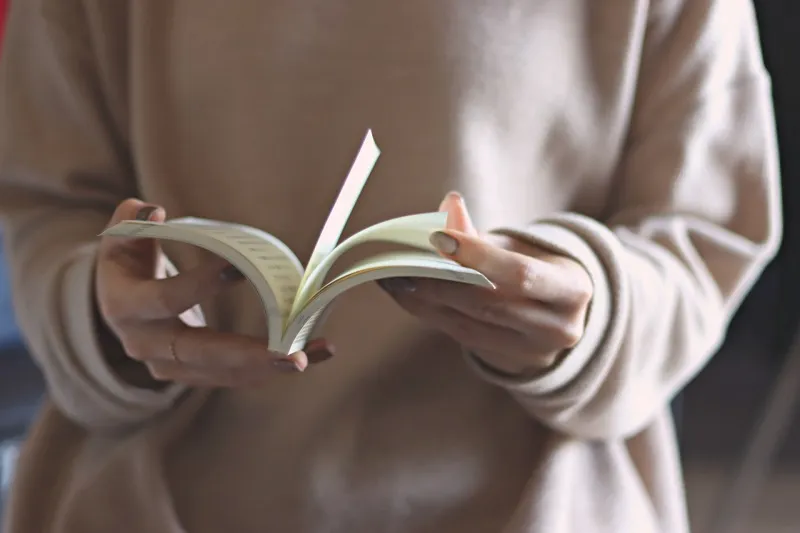江戸時代の初等教育「寺子屋」を紐解く!

突然ですが、「寺子屋」ってご存じですか?
江戸時代の上方において、寺院で手習師匠が町人の子弟に読み書き・計算等を教えた学問施設の事らしいです。
実際どのような役割を果たしていたのか、今回は「寺子屋」を紐解いていきましょう。
寺子屋ってなに?
寺子屋(てらこや)とは、江戸時代の上方において、寺院で手習師匠が町人の子弟に読み書き・計算等を教えた学問施設の事です。
江戸時代の日本は知識層に限らず、一般庶民の識字率もかなり高い時代でした。
江戸幕府によって天下が安定し、太平の世が続くと経済が発展し、あらゆる階層の人たちに読み書きや計算の基本能力が求められるようになったためです。
庶民の初等教育は、全国に自然発生的に広まった「寺子屋」という私塾が担いました。
「手習い」「手跡指南」とも呼ばれ、江戸時代末期には全国で六万以上の寺子屋が存在していたと考えられています。

どんな勉強をしてたの?
一般的に「読み・書き・そろばん」を中心に学習し、学ぶ時間は主に朝五ツ(午前八時頃)から昼八ツ(午後二時頃)まで。
その間に昼九ツ(正午)に昼食の時間があることが多かったようです。
因みに「寺子屋」という名称は、鎌倉時代に僧侶が寺院に子どもたちを集め、読み書きを教えたことに由来します。
寺子屋に通う子どもたちの年齢は7歳から14歳と一律でなく、教育内容も各寺子屋によって違いがありました

例えば商家の子どもが集まるような寺子屋では、商用文の読み書きのためにくずし字を、女子には裁縫を教えるなど、花嫁教育を施すこともあったようです。
現在の学習塾業界も個別指導ができるところへのニーズが高まっていますが、寺子屋ではすでに、一人ひとりに合せた個別カリキュラムが組まれていました。
当然、授業料のようなものもありました。
入学金にあたる「束脩(そくしゅう)」、月謝にあたる「月並銭(つきなみせん)」などを収める必要がありましたが、各寺子屋によってその金額は異なっていたようです。
また、各家庭の経済状況に合わせて金額が決められていたため、たとえ貧しい家の子どもでも、等しく教育を受けられるようになっていたようです。

その後はどうなったの?
最初は各都市部を中心として成立した寺子屋は、発展していくにつれて地方にまで波及したそうです。
19世紀以降には全国的にその数が増大したといいます。
江戸時代の教育インフラとなった寺子屋は、日本が西洋式の近代教育を整える中で徐々に役目を終えていきますが、指導者がそのまま学校の指導者になるなど、その後の日本の教育を支える礎となったのです。
現代版「寺子屋」が東京都内にある!?
東京都目黒区にあるアフタースクール寺子屋
アフタースクール寺子屋は大きな一軒家、スタッフによる徹底送迎、英語・そろばん・書道を毎日繰り返し学習する、ということが特徴の学童保育です。
徹底した基礎学力の向上を目指しながら、学童保育では安全第一にメリハリをつける生活を送る力、自分で考える力、自ら学習する習慣を身に付けます。
また、働くお父様・お母様にはスタッフ全員が寄り添い、お忙しい保護者様を徹底的にお支えします。
【施設名】アフタースクール寺子屋
【アクセス】東京都目黒区碑文谷3-14-16
東急東横線 都立大学駅 徒歩10分
【電話番号】03-6412-7832
この記事を書いた人
『イートラスト株式会社 CS・テクニカルチーム 課長/ B-rise運営事務局 副局長』
飲食業界で現場・SV・マーケティングを経験し、2014年イートラスト株式会社へ入社。ディレクター業務・カスタマーサポート業務を経て、現在はSEOやホームページ運用全般を請け負う「テクニカルチーム」を立ち上げ、責任者を担う。飲食業界に携わっていたこともあり、サービス業様へのWebマーケティング・SEO/MEOで貢献していくため、日々新しい試みを模索している最中です。