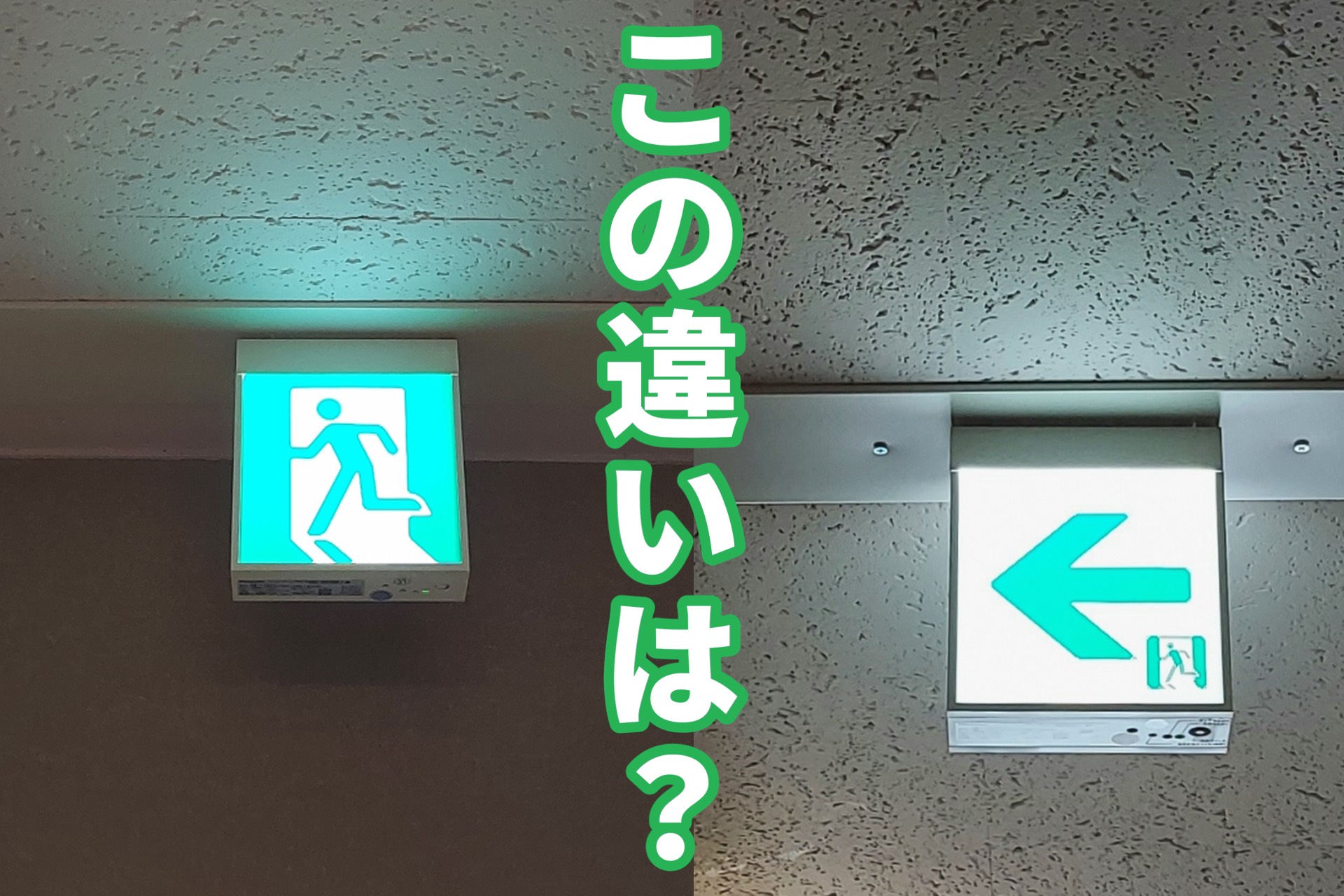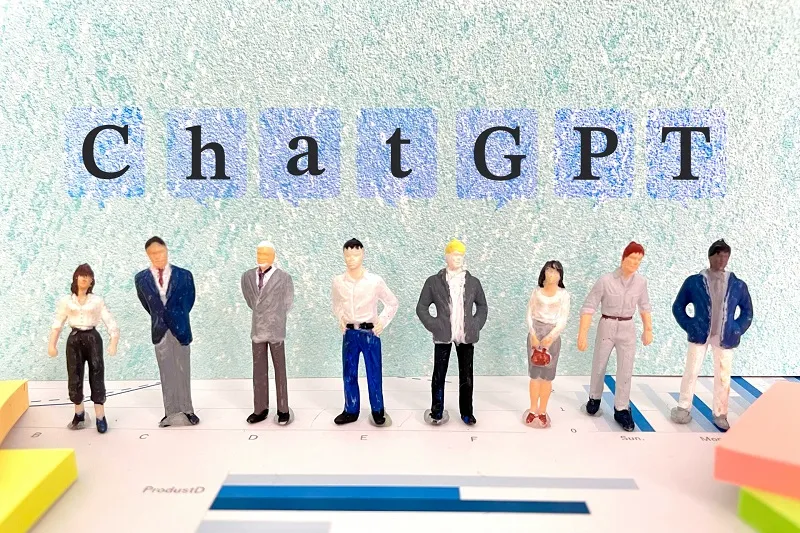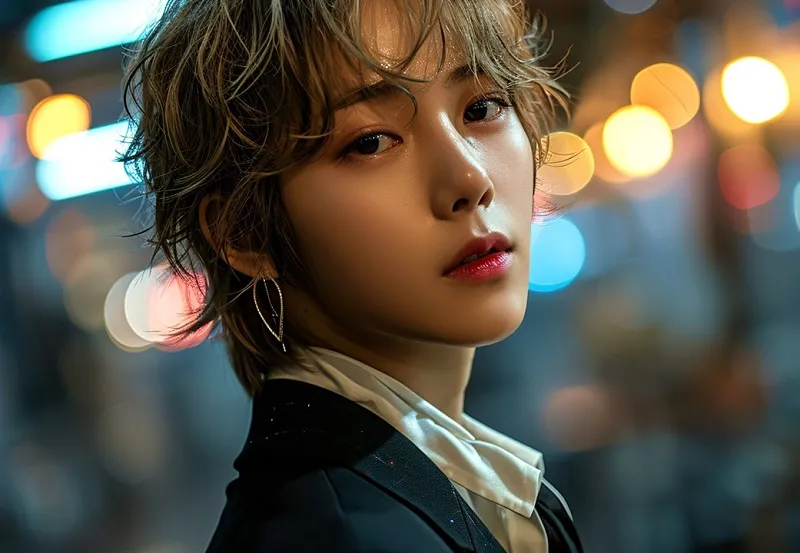2023 年 8 月 14 日公開
「360度評価」ってなに?うまく運用するコツとは

会社で働く以上、能力を評価されて役職や給与が決まります。その評価方法は会社によって異なり、明確な基準がある会社もあれば、上司に委ねられている場合もあります。
その評価方法の中でも、今回は上司だけではなく同僚なども評価に参加する「360度評価」に関してのメリットやデメリットを紹介したいと思います。
「360度評価」とは
「360度評価」とは、一人に対して上司だけではなく、同僚や自分自身も評価を行う方法です。一般的には被評価者の上司がその人の評価をしますが、360度評価においては、他部署の人や同僚、部下などいろいろな関係者からの評価を受けることができます。
上司だけの評価よりも、被評価者が納得しやすく、多くの視点から自身の強みや弱みを理解することができます。
360度評価のメリット
評価が客観的になる

従来の上司一人による評価では、上司の主観が大きく関係してきます。上司が気に入ればいい評価になり、気に入ってもらえないと才能があっても評価は下に付けられてしまいます。
評価に主観が入ることで公平ではない評価になってしまいます。
しかし、360度評価は上司以外にも同僚からの評価や、他部署からの評価、部下からの評価など、多くの人からの評価が入ってくるので、客観的に見た広い視点での評価が下されます。
評価に納得しやすい
評価する人が上司のみで、主観が入ってしまうと「こんなに頑張っているのに、評価されない!」などの不満が生まれてくる可能性があります。
評価する人が多く、客観的な評価であれば、客観的な意見となるので納得しやすくなります。
自分のことが理解できる
たくさんの人に評価されることで、自身の強みや弱みがより分かり易くなります。
普段指摘できないようなことや、思っていても言えないことなどを伝えることで、より深い自分の受け取られ方を理解することができます。
上司が見えないところも見える
上司の前ではへこへこしている人でも、部下の前では悪い一面があるかもしれません。 そういった場合は、上司のみの評価では組織として正しい評価にはなりません。多くの人や多くの立場から見たからこそ見える面を知ることができるので、より正しい評価になります。
上司の目が行き届いていなくて、見えなかった、知らなかったいい点などを知るきっかけにもなります。
上司の育成になる
上司というのは、部下よりも上に立って全体を俯瞰して、チームの一歩先を行く必要があります。
しかし、全体を見るのが苦手な上司もいたり、数字重視の上司もいたりします。
普段見えていなかったことに改めて気づけて、普段部下が思っている不満や信頼されているかも可視化することができて、そのあとの仕事のやり方を改善することもできます。
360度評価のデメリット
メリットが多い360度評価ですが、デメリットも存在しています。
上の人の評価がよくなりやすい
全員がいろいろな立場の人の評価ができるとなると、上司の評価は悪くつけにくいですし、部下のことは低く評価しやすいです。
忖度した評価をしてしまうと、上司がいつまでもいい評価となり、部下がいい評価になることがなく、ステップアップのチャンスが少なくなってしまいます。
馴れ合いの評価になる

評価する者同士の仲がいい場合、「いい評価付けとくから、私のも良くしておいて」などと、いい評価を付けあう人たちが出てきます。
それによって正しい評価ができなくなってしまう場合もあります。評価者の選択時はそのようなことにも注意が必要です。
同僚に不信感が生まれる

人が人を評価することで、自分のマイナス面も指摘されてしまう場合があります。
同僚の中にそう思っている人がいると、受け止められる人であればいいですが、納得できない場合は誰が言ったのか分からず、不信感につながる要因になってしまいます。
360度評価を上手に行うコツ
いい部分もありますが、デメリットもあるので、ここでは360度評価を意味のあるものにするコツを紹介します。
評価者は多くする
360度評価はなるべく多くの従業員が評価者になる方がいいです。
2~3人などにしても、仲のいい人同士で馴れ合いの評価をするだけなので、多くの評価をもらうため10人など多めに設定して、そんなに仲は良くない同僚などからも評価されるようにするのがおすすめです。
成長度や貢献度など多くの側面で評価する
貢献度や作った数字のみで評価した場合、基本的に歴が長い従業員の評価が高くなってしまいます。
それでは意味がないので、貢献度や数字以外にも期待されている内容に対しての仕事量や、成長度などを重視して評価をするように統一すべきです。
ここの評価者が期待することに到達しているかは、人によって違うので順位がばらけて面白い結果になります。
また、歴が長い人を成長度で評価して、部下が忖度しなければ、上も成長し続けるために常に成長しようとするので、組織全体の能力向上にもつなげられます。
段階評価などだけでなく、具体的な評価をさせる
段階評価のみでは、たくさんの評価者を評価する際に適当になってしまう可能性があります。また、馴れ合いの評価もしやすく公正さが失われます。
対策として「良かった点」や「改善点」などを具体的に記載させることで、説得力があり、具体的な評価ができて、最終評価者の上司や人事の判断もしやすくなります。
全体に高すぎる評価はできないようにする

自由に評価できる場合、全員に高くつける平和主義者も生まれてしまいます。
それでは公正な評価ができませんし、改善点を知ることができないので組織としての成長を阻害してしまう可能性もあります。
複数人を評価する場合は、平均点を普通以下にする相対評価で行うことで、全員の評価を高くつけることを防ぐことができます。
評価を本人に伝える
せっかく多くの人から評価が集まったら、本人にすべて伝えましょう。
万が一感情が入っている評価があった場合は、上司がそれを伏せる方がいいですが、マイナスもプラスも本人に伝えましょう。
マイナス面の中には自分が気づいていない面があって、指摘されることで改善することができるかもしれません。
評価者が誰か分かるようにする

最終評価者は誰がその評価をしたのか分かるようにしておく必要があります。
匿名で評価させると、何でも言っていいと勘違いする人が出てくるので、誰が何を評価したのか把握しておくのが重要です。
その評価に対して、直接評価者と話したり、真意を確認したりすることも必要です。
しかし、軋轢を生まないためにも、誰が何を言ったか本人には言わない方がいい場合もあります。
評価の平均を基準にする
多くの人からもらった平均値をもとに数値化し、他の人と比べて上か下かをはっきりさせます。その評価が客観視した意見の平均になりますので、上司や評価者はそれをもとに感情無しで判断します。
上司への貢献度はもちろんですが、全体への貢献度が重要なので客観視した意見を参考にする方がいいです。
評価後に全員でその評価について話す

これは、評価方法やチームのメンバー、組織の考え方にもよりますが、同じチーム内でその評価について話した方が、納得感が大きくなります。
直接意見を言う場所にしたり、「もっとこんなにいいところがあった」などと他の人に伝えることもできるので、いい機会になります。
その発言の結果、他の人の評価が変わることもあります。
ということで今回は評価制度である「360度評価」について紹介しました。
メリットもデメリットもあるので、使い方によってはチーム内や組織内に軋轢を生んでしまうこともあります。しかし、うまく使うことで組織全体を、より客観的な目で評価することができて、お互いに成長を促すこともできます。
この制度を取り入れる際は、組織に合わせてルール化して、より俯瞰した意見を集められるようにしていく必要があります。
この記事を書いた人
『イートラスト株式会社 テクニカルチーム』
青森県出身。8年間、小売業界に従事しつつ趣味でライターとして活動。大手サイト(Yahoo!、朝日新聞社)の記事投稿やTokyoFMのラジオ出演の経験も。2022年にイートラストに入社。好きなものは家電、インディーズ音楽、動画編集。