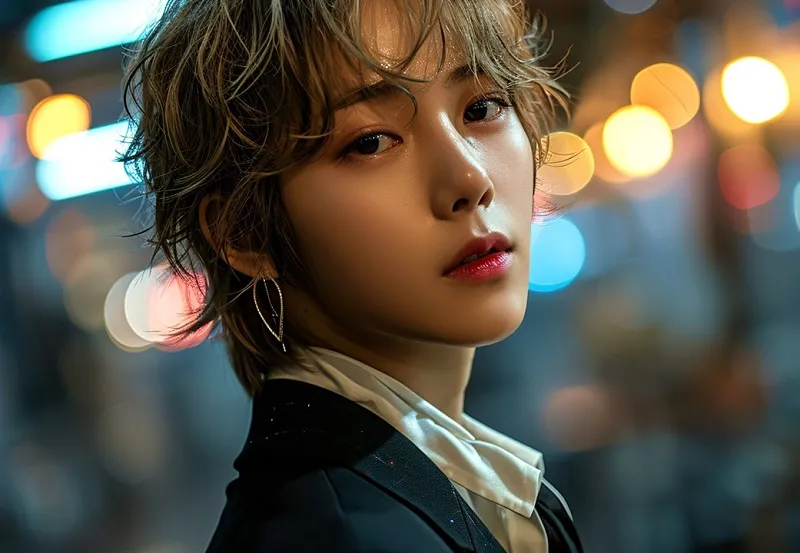2022 年 9 月 1 日公開
知っているようで知らない?B級グルメってなに??おすすめのグルメもご紹介!

「B級グルメ」という言葉はよく聞きますが、そもそもB級グルメとはどのようなものなのでしょうか。
今回は知っているようで意外と知らないB級グルメの定義やおすすめの「B級グルメ」をご紹介させていただこうと思います。

1.B級グルメの定義とは?
一定の地域で提供され、価格が安く、食材も贅沢なものではないのに美味しい、地元で人気のある庶民的なグルメのことを言います。
2.C級グルメってあるの?
「C級グルメ」という言葉はまだまだ普及はしてないですが、B級グルメよりも限定された地域の料理やマイナーな食材(いわゆるゲテモノ)を使った料理のことを表現することが多いです。
また自虐的なへりくだった意味合いで使われることもあります。
例えば、食パンに水溶き小麦粉とパン粉をつけてラードで揚げる感じで焼いた「パンカツ」は八王子のC級グルメとして親しまれています。
3.おすすめ!関東のB級グルメ!
ゼリーフライ/行田フライ

「フライ」「ゼリー」というものの、肉や魚を油で揚げた「フライ」やお菓子の「ゼリー」とはまったく違う食べ物。
「ゼリーフライ」という名前の由来は、小判のような形から。
「銭フライ」と呼ばれていたのが変化し、「ゼリーフライ」と呼ばれるようになったと言われている。
見た目は衣の付いていないコロッケのようだが、たくさんのおからとジャガイモをベースに、ニンジンやネギなどが入っているのが特徴。
ソースによる味付けとモチモチとした食感が相まって、地元民から愛されている。
そのルーツは、中国の東北地方にある「野菜まんじゅう」という料理。
日露戦争に従軍した、行田市内の「一福茶屋」の店主が考案したと言われている。
明治後期には一般的に食されるようになり、現在まで行田市民のおやつとして愛されている。
<引用:うちの郷土料理>
サンマ―メン

神奈川県のご当地ラーメン!
もやし、白菜、豚肉などを入れた野菜炒めにスープを入れ、とろみをつけてラーメンに乗せた、横浜発祥の麺料理。
その名の由来や漢字については諸説あるが、一説によると「生馬麺」と書き、これは「新鮮でシャキシャキした素材を上に乗せた麵」の意味になるという。
戦前から横浜中華街では肉そば(ルースー麺)がよく食べられていたが、高価だったため、まかないとして野菜入りの麺料理「サンマーメン」が作られるようになった。
野菜あんをかけることでスープが冷めにくく、ボリュームもあることから人気となり、やがて県内各地の中華料理店がメニューにとり入れていった。
今では県内のラーメン店や中華料理店にはサンマーメンを主力とするところも多い。
横浜市民、神奈川県民にとって、サンマーメンは日常的によく目にする慣れ親しんだ品となっている。
<引用:うちの郷土料理>
月島もんじゃ

もんじゃはゆるく水で溶いた小麦粉に具材を混ぜて鉄板で焼き、めいめいのヘラで熱々を食する料理。
江戸時代末期、月島の駄菓子屋の前で手頃なおやつとして売られていたのが根源である。
食料難であった昭和20年代頃、うどん粉を溶いて醤油やシロップを加えたシンプルなもんじゃ焼きが子どもたちに広く親しまれていた。
江戸末期から明治にかけては物資が不足していた時代、紙や習字の道具をなかなか手に入れることができなかった子どもたちに、小麦粉を水に溶いた生地で鉄板に文字を書いて教えたり遊んだりしていたことから「文字焼き」と呼ばれ、もじがもんじと転じて「もんじゃ」へ変化していった。
戦後の経済成長に伴い、キャベツ、コーンや揚げ玉など具材を入れて進化していったが、同時に子どもたちが親しんできた駄菓子屋は激減してしまう。
幼い頃から親しんできた味を残そうと数軒のもんじゃ焼き店が立ち上がり、大人のつまみへと変化を遂げ、現在に至る。
もんじゃ焼きに必須なのが、鉄板とヘラ。
もんじゃ焼きは生地の外側から少しずつすくい、鉄板に押し当てて焦がして食べるのが一般的だが、現在は実にさまざまな具材のバリエーションに富んでおり、様々な味ともんじゃの食感を楽しむことができる。
<引用:うちの郷土料理>
勝浦タンタンメン

勝浦のタンタンメンは、当地の海女・漁師が寒い海仕事の後に、冷えた体を温めるメニューとして定着していた。
基本スタイルは醤油をベースにしたスープに中華麺が入り、具材としてラー油や唐辛子で炒めた玉ねぎと豚挽き肉が載っている。
一般的な担担麺に使われるゴマや芝麻醤は使用しない。
メニューの特徴は、通常のゴマ系と違い、醤油ベースのラー油が多く使われたラー油系、タマネギとひき肉、にんにくをしっかり炒めた具が特徴のタンタンメン。
<引用:Wikipedia>
他にも全国にはたくさんの美味しいB級グルメがあります。
ぜひ今度のお休みはB級グルメを目的に旅してみてはいかがでしょうか。