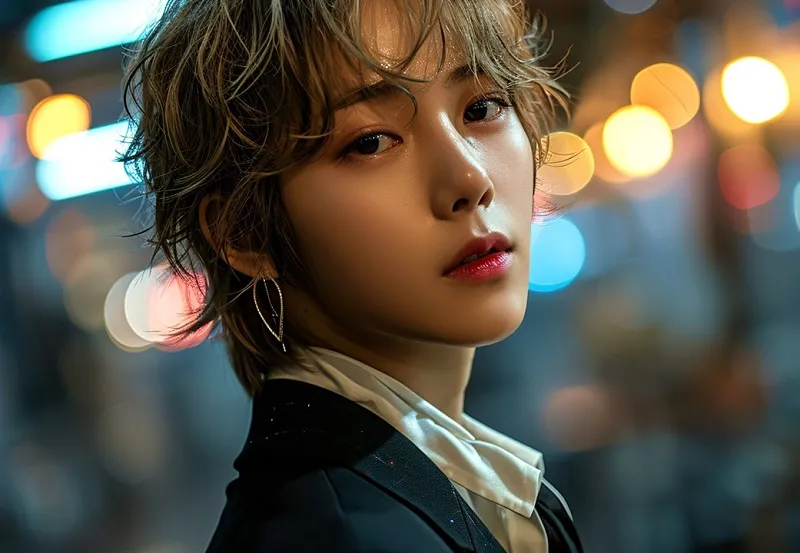しめ縄や鏡餅などの正月飾りはいつからいつまで飾る?何のための飾りなの?

お正月といえばしめ縄や門松、鏡餅などの正月飾りが各地で販売されています。
昔からの見慣れた光景ですが、なぜ正月飾りを飾るのでしょうか。
今回は正月飾りの意味やいつからいつまで飾るべきなのかなどを紹介していきます。

正月ってそもそも何?
正月は各暦の年始めのことをいい、正月飾りをして、お節料理などを食べてお祝いします。
期間としては明確に決まっておらず、1月1日~3日までの「三が日」を言う場合もあれば7日までの「松の内」の期間とすることが多いです。
正月はなぜお祝いするの?
もともとはお盆と同じ意味を持っており、祖先の霊を呼び慰霊するものでした。
それが次第に分化して、お祝いを行うものになりました。
年神様が訪れ、その年の豊作と無病息災を約束してくれるので、それをお祝いするためにする行事ともいわれています。
代表的な正月飾りの意味
正月飾りは、いくつかのものがありますが、具体的にどんなものがあるのか紹介いたします。
門松

門松は家の玄関や門前に飾られる、松や竹からなる飾りです。
昔は木の梢に神が宿ると考えられており、年神様を家に迎え入れるための目印として置かれるものです。
しめ飾り

神社の鳥居など、神様をまつる場所と現世の境界に設置されるのがしめ縄です。
そのしめ縄に橙や裏白と呼ばれる植物をつけて飾ったものを、しめ飾りといいます。
橙は家が代々続くこと、裏白は葉の裏が白いことから、白髪になるまで長生きすることを祈っています。
門松同様に玄関に飾られることが多いですが、神棚、トイレ、勝手口などに飾られることも多いです。
鏡餅

鏡餅は昔、神事に使われてきた青銅の鏡がモチーフになっており、神様が宿ると言われています。
鏡餅は神が宿る場所になるので、床の間や神棚に飾るのが理想です。
それがない場合は、リビングなどに置きましょう。
正月飾りはいつ飾る?
正月の飾りは、いつ頃飾るのがベストなのでしょうか。
実際に飾られる日にちで多いのは、12月26日~28日に飾るケースが多いです。
最もいいと言われているのは28日で、末広がりの意味を持つ「8」が付くことで縁起がいいと考えられています。
ちなみに29日は「二重苦」や「苦持ち(餅)」「苦待つ(松)」などを連想させるので、一般的には避けた方がいいといわれています。
また、31日は元日までたったの1日しかなく、神に失礼という理由で「一夜飾り」といわれてあまりいいとされていません。
正月飾りの片づけはどうする?
鏡餅以外の飾りの片づけは、松の内が過ぎたら外すのが目安となっています。
一般的には7日で、関西などでは15日とされています。
その後1月14日か15日に神社で行われる「左義長」にて燃やして処分するのがいいとされています。

持っていけない場合は燃えるゴミで処分するしかなくなるかもしれません。
その際は、お清めしてから捨てた方がいいみたいです。
鏡餅を食べるのはいつ?
鏡餅は1月11日に鏡開きをするのがいいとされています。
最近はプラスチックの餅型ケースに、切り餅が入っていることが多いので、そのまま開封して食べるだけです。
ということで今回は、正月飾りの紹介でした。
スーパーやコンビニなどで気軽に買えるものの、意外と知らない方も多かったのではないでしょうか。
今年は正しい飾り方でお正月を楽しみましょう!
この記事を書いた人
『イートラスト株式会社 テクニカルチーム』
青森県出身。8年間、小売業界に従事しつつ趣味でライターとして活動。大手サイト(Yahoo!、朝日新聞社)の記事投稿やTokyoFMのラジオ出演の経験も。2022年にイートラストに入社。好きなものは家電、インディーズ音楽、動画編集。