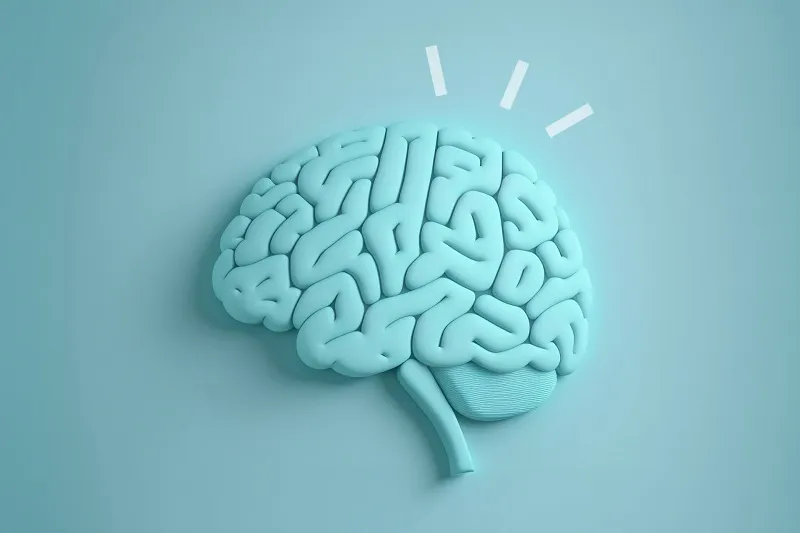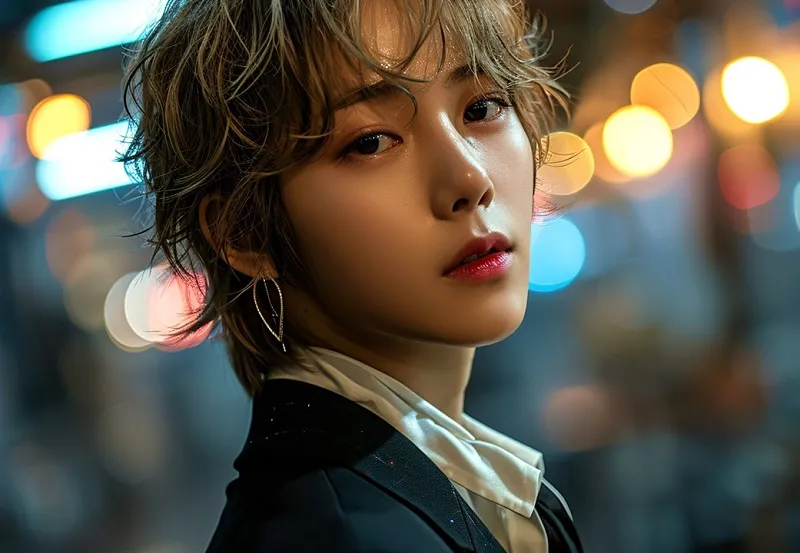XR技術の教育現場での活用法とは?
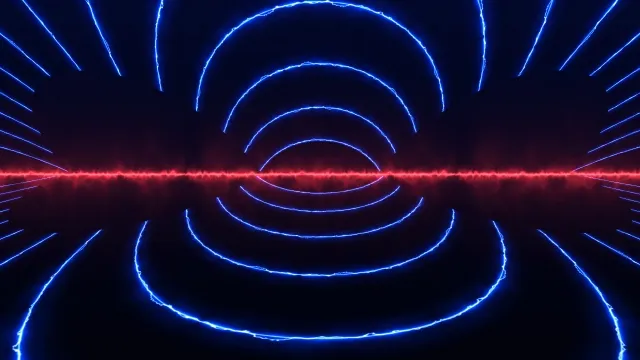
最近のIT技術の発展によってメタバースという言葉が普及し始めてきていますが、
メタバースとはそもそもなにを指すことばなのか?
XRとは何が違うのか?
意外と知らない人も少なくないのではないでしょうか?
今回はメタバースとXRの違い、その技術の教育現場での活かし方についてご紹介致します。
メタバースとXRって何?
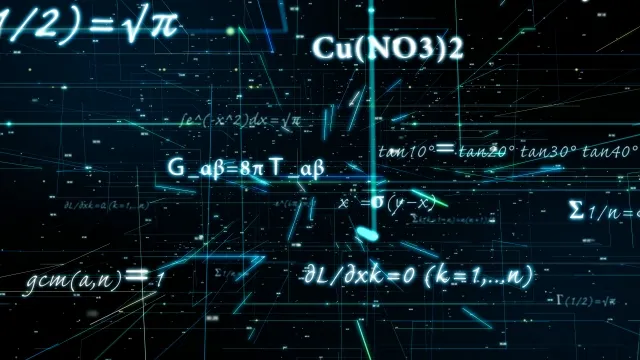
メタバースとは「Meta(超越した)」「universe(宇宙・世界)」を掛け合わせてできた造語です。
オンライン上の仮想空間やそこで提供されるサービスのことを指して呼びます。
類似するコンテンツとしてXRというものがありますがメタバースとの違いについてあなたは説明することができますか?
XRとは現実に存在しないものや情報を表現、体験できる技術の総称でVR(仮想現実)、AR(拡張現実)、MR(複合現実)のことを指します。
メタバースとVRはほとんど同じではないかと考える人もいらっしゃいますが、VRゴーグルをつけ仮想空間で活動していても、オンライン上で交流することができなければメタバースではありません。
仮想空間内にいても実際に近くで集まる必要があるものはメタバースの定義からは外れてしまうのです。
XRと教育現場

すでに幅広いジャンルで活用されているXR技術ですが「教育」に取り入れるとどのような活用方法があるのかご紹介します!
①立体映像を用いた授業
コロナウイルスによってリモート学習を導入した学校が増えましたが、リモート学習では教師の顔を見ながら学習をすることはできても従来の授業と同じように受け身のスタイルになってしまいます。
立体映像を伴った授業であれば口頭、文章だけで説明するより生徒の理解も深く一人一人に教材を用意するコストの削減にもつながります。
②イメージの具現化
授業で教科書をテキストとイラストで読むだけだと、説明や問題を頭の中で具現化することが苦手な生徒は頭の中でうまくイメージが出来ず、なかなか知識として身につかないということもあります。
しかしXR技術を用いた授業を行うことで実験の様子を実際に体験できたり、図形の問題を立体でみることによってより学んだことが身に付きやすいなどの沢山のメリットがあります。
火を使う実験などでは本物の火を使うわけではないので失敗して事故を起こす心配もありません。
最近ではXR教育を取り入れている高校もあるので、今後その数はさらに増えていくことでしょう!
最後に
XR技術を身近で体験できる場として東京タワーの中に『RED° TOKYO TOWER』という新体験テーマパークが、今年4月20日にグランドオープンしたので是非お休みの日にあなたたも体験してみてはいかがでしょうか?