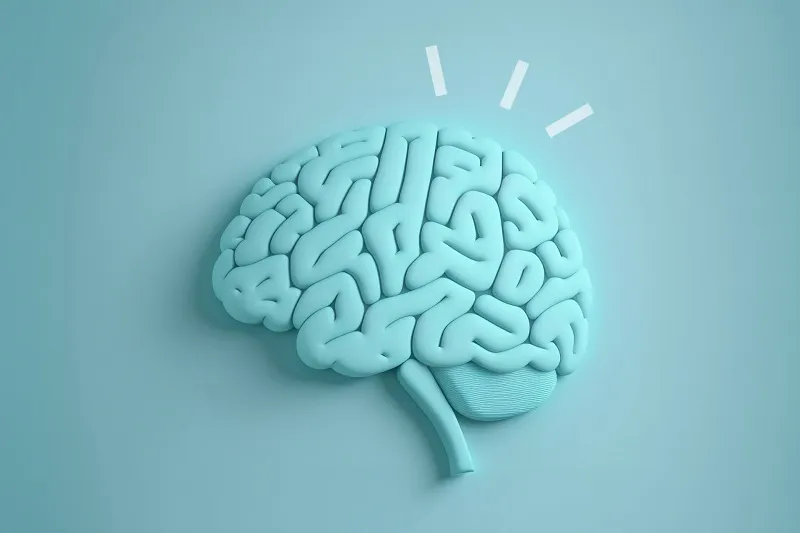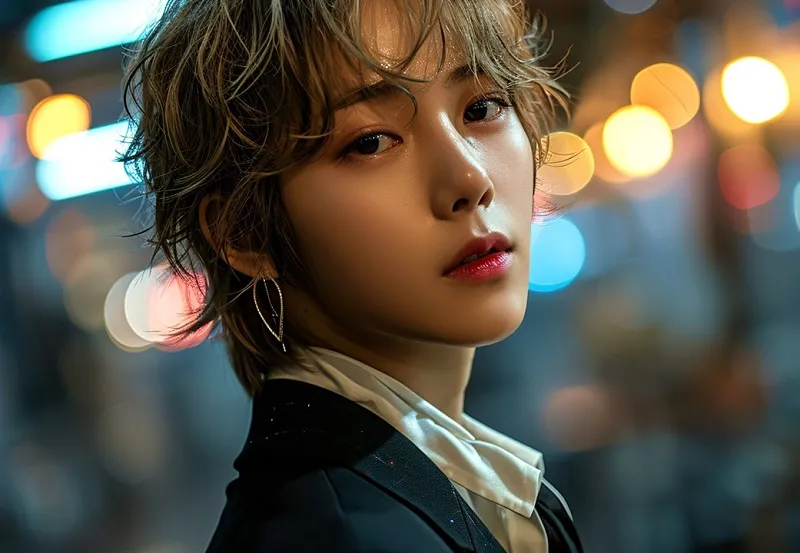社会人に求められる能力をあなたは持っていますか?

社会に出て必要とされる能力やスキルは、学校では教えてくれません。
そのことに気づくのが社会人になってからの場合が多いでしょう。
電話の出方、メールの送り方、ビジネス会話の流れなど、社会に出て初めて学びます。
学校で学んできた国語、数学、理科、社会などの知識は、それを生業にする一部の職業の人しか大活躍しないのではないでしょうか。
学生の間は受け身でも問題ないですが、社会人はそうではありません。
受け身だと仕事ができない、やる気がないという印象を相手に与えてしまいます。
主体的に向上心を持って何事にも取り組むこと、自分の言動・行動の責任をもって応対することが大切です。
そこで、今回は社会人に求められる能力について紹介したいと思います。
真のコミュニケーション力

”コミュニケーション力が高い”というと、どういう人をイメージされますか?
「初対面でも話しかけられる人」「友達が多い人」など、思い浮かべる人も多いのではないでしょうか。
表面的なことでいえば、この状態だけでは「コミュニケーション力がある」という判断になります。
真のコミュニケーション力の高さとは、「相手が何を求めているかを見抜き、相手が聞きたいことを話すこと、相手が話したいことを聞くこと」です。
自分が話したいことをペラペラ話しているだけでは、ビジネスにおいて、「話好きな人」「自己中心的な人」という印象になります。
相手にストレスを与えた時点で、コミュニケーション力が高いとはなりません。
相手ありきで、相手との関係性においてバランスをとることが重要です。
つまり、<気が利くか>がポイントになります。
コミュニケーション力を高めるためには?
・傾聴力を鍛える

- 「聞く」音や声などを自然に耳に入ってくること
- 「聴く」積極的に耳を傾けること
自分の話をするよりもまずは相手の立場になって物事を考える必要があります。
そのためには”聴く”ことを意識します。
ただ単に”聞く”だけでは相手が話すだけや相手を質問責めになるなどバランスが取れません。
傾聴力とは、相手が話しやすい雰囲気を作り出し、話を聞くときの相づち・目線・表情・声のトーン・間の取り方を工夫し、相手の話の背景の価値観や気持ちなども深く理解、共感しながら"聴く"力です。
・話をする前にまず考える

コミュニケーションは相手との関係性で成り立ちます。
友達とのプライベートの会話では何も考えず思ったことを言うだけでもいいかもしれませんが、ビジネスにおいては良しとされません。
「なぜその話題を話すのか」という目的意識や根拠をもって話さないと「自分の話したいように話す人」「この話に何の意味があるのか?」と思われてしまいます。
「なぜ」を掘り下げて、そこに「~だから」という根拠を考えるようにしましょう。
・相手の話を評価しない
話を聞いていて、わかった気になると早く結論を出したがったり、次の話題に移行したい気持ちが芽生えることもあるでしょう。
そうすると、相手の話を無意識に判断して聞く姿勢を失くしてしまうことにつながります。
話を聞くときは、「相手がただそう思っている」という観点を持ち、割り切って客観的に話しを聞き続けることを心掛けることが必要です。
相手の話を序盤で評価してしまうと、この「割り切って客観的に話しを聞き続ける」ということができなくなります。
話を聞きながら自分の脳内に浮かんだ評価感情をシャットアウトすること。これが重要です。
おすすめ書籍
仕事で必要な「本当のコミュニケーション能力」はどう身につければいいのか?
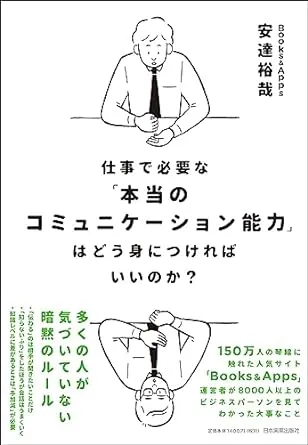
未来を予測 先読み姿勢

未来を予測(想定)しながら、仕事をしていますか?
1つの物事を行うことで、多方面に影響が出る可能性は少なくありません。
論理的に考えて、予測することができないと、目の前のことしか対応できない人間になります。
「本当にこれでうまくいくのか?失敗する可能性はないのか?」と自分の選択・行動に対して、客観的・批判的に繰り返し思考を重ねることで、予測不可能な事態を最小限に抑えることができます。
先を読むとは具体的にどうすればいいのか?
・事実や根拠と認識の誤差を少なくする
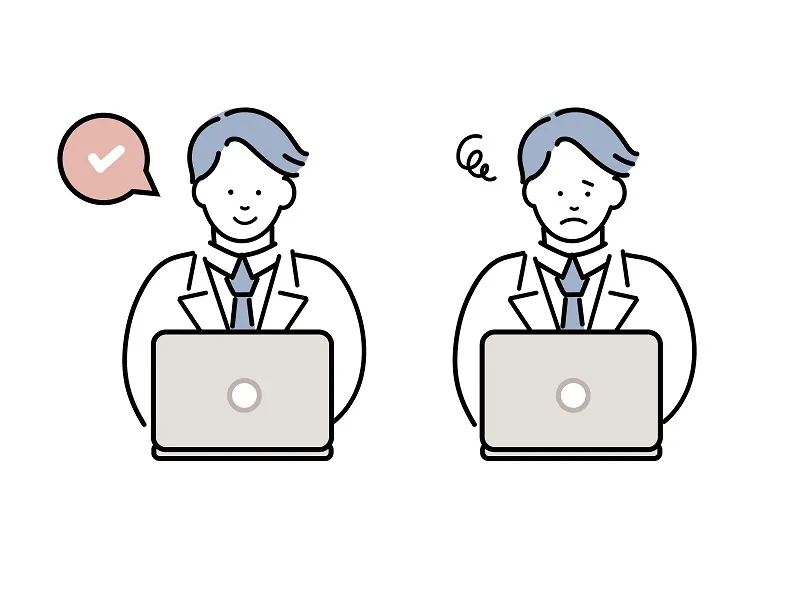
自分の行動に過度な自信を持っている人に起こりがちですが、物事に対して自分の認識が間違っていないという思い込みが強いと、未来を予測しても成功するビジョンしか描けない人がいます。
この考え方自体は悪くないですが、物事の判断基準が事実や根拠ではなく、自分の能力に向いているので、認識がズレていると簡単に失敗します。
あくまでも謙虚に、自分の行動に過度な自信を持たないこと、これが事実や根拠と認識の誤差を少なくすることにつながります。
・事前確認を行って、計画破綻の可能性を最小限にする
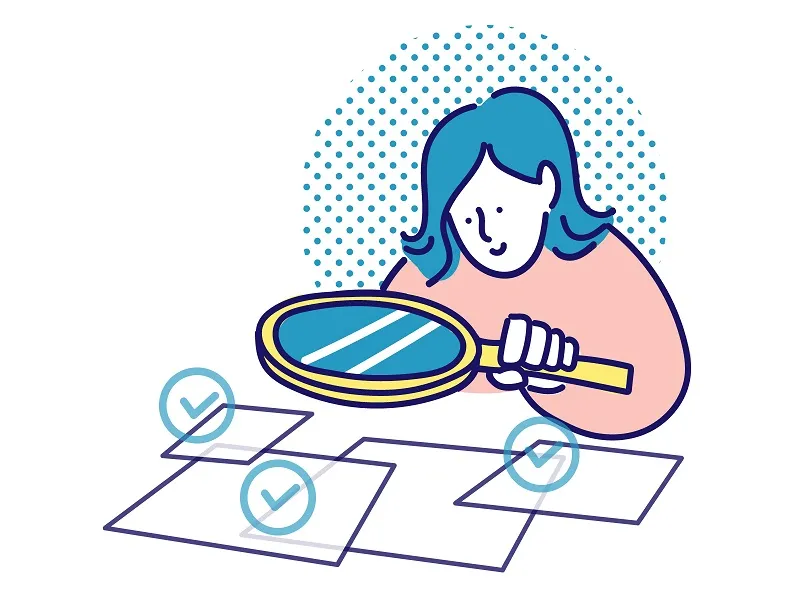
プレゼンや提案を行うときにある程度Q&Aを用意すると思います。
しかし、問いの方向性が1つだけだったり、解釈が1通りしかないと判断してしまうと、方向性が異なったり、別の角度からの解釈に対応ができません。
例えば・・・「部署の忘年会をやろうと思うが、外食と社内どちらがいい?」とメンバーに聞いたとします。
そこで、みんなから社内がいいと回答が返ってきたが、社内規定でアルコールNGだったとします。
のんべえばかりの集まりの場合、そもそもこの時点で計画が破綻します。(なぜ事前確認をしておかなかったのか?となります)
この1つの事象だけでも、計画段階で考えなくてはならないことはたくさんあります。
- 社内で忘年会を開催するにあたって、アルコールはOKなのか
- 食べ物の手配はどうするのか
- 食べ物のにおいが社内に充満してもいいのか
- 他の部署で仕事をしている人はどう思うのか・どう映るのか
何を聞かれても答えられる・対応できるように、あらゆる可能性を網羅的に考えること、自分の認識が絶対ではないという意識をもって、俯瞰する視野を持つことが大切です。
おすすめ書籍
できる人が続けている「先読み仕事術」 (DO BOOKS) 単行本
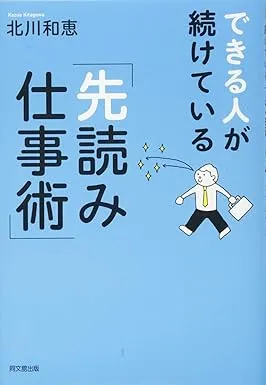
頭の回転の良さ

勉強ができると仕事ができるは別物だと言われることが多いですよね。
勉強ができるとは、答えが決まっていることに対して回答を導けること仕事ができるとは、答えが決まっていないことに対して、最適解を迅速に導けること、を指します。
社会に出ると答えがないことや白黒はっきりつかないことばかりです。
その状況を受容し、臨機応変に対応できる頭の回転の良さが重要視されます。
頭の回転が良いとはどういうこと?
・物事の関連性に気付けるか

仕事を行う上で、応用がきかないと成り立ちません。
応用がきかないとは、教えたことはできるけど、組み合わさったときに対応できない、組み合わせて対応することができることに頭が働かないことです。
算数にあてはめると、「1 + 1=2」「10-7=3」はできるけれど、(教えてもらっていないから)「(1 + 1)+(10-7)=5」はできないというタイプのことです。
今まで収集した知識Aと知識Bを掛け合わせることができる、その可能性に気付けるかというのがポイントです。
・やり方に固執せず臨機応変に対応できるか
例えば来客のお茶出しで「夏は冷茶、冬はホットコーヒーを出すように」と教わっていたとします。
しかし、冬なのにもかかわらずポットのお湯が足りなかったとしましょう。
あなたはどうされますか?湯が沸騰するまで待ちますか?そう考えた人は物事の本質に気づけていません。
ここで何よりも重要視されるのは、「打ち合わせ序盤でお茶を出す」ことです。
冬に冷茶を出してはいけない決まりはありません。しかし、言葉通りでしか受け取れないと「冬は絶対にホットコーヒーを出さないといけない!!」と自動変換されるのです。
「夏は冷茶、冬はホットコーヒーを出すように」と言った先輩も、気温に合わせて相手を気遣ってねという理由から発した言葉です。
これに気づくことができるかで、臨機応変に対応できるかという能力に差が出ます。
おすすめ書籍
メタ思考~「頭のいい人」の思考法を身につける
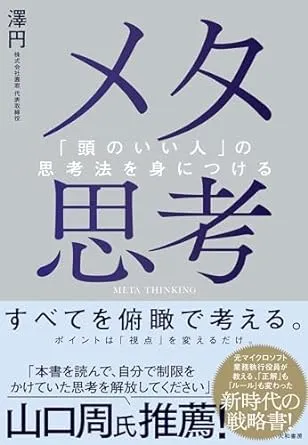
スケジュール管理力

仕事を行う上でおろそかにできないのが「スケジュール管理」。
丁寧に仕事をこなすことは大事ですが、それは「納期」を守ってこそ。
完璧にしたいからといって納期を過ぎるのはただの仕事ができない人です。
スケジュール管理をする上で大事なこと
・優先順位付けをする

1か月、1週間、1日の中でも多種多様な仕事内容があります。
仕事の依頼順に対応していくと、すべてを希望通りに対応することができません。
仕事の依頼内容、納期に合わせて、優先順位を3段階ほどに設定します。
- 高:納期が短いor緊急性が高い
- 中:納期が通常or緊急性もあまりない
- 低:納期が長いor緊急性が低い
優先順位をつける癖を日ごろからつけていれば、急な対応にも焦ることはありません。
優先順位は自分の中の優先順位、相手の中の優先順位が必ずしもイコールではないことを理解した上で、依頼・相談をするという意識も忘れないようにしましょう。
・納期を段階的に設ける
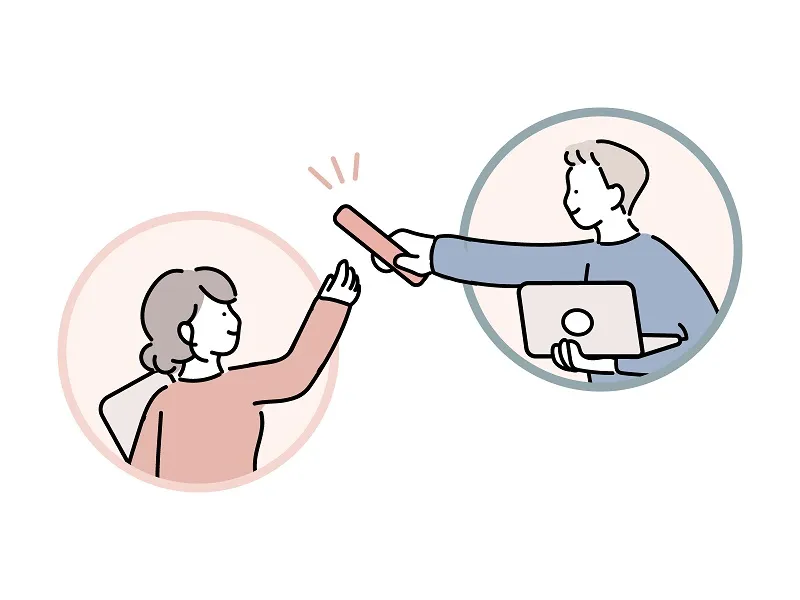
自分だけのことでない場合、相手の動きをコントロールできないと理解することが必要です。
複数の人、複数の会社が関わって1つのことを行う場合、最終提出先の納期をデッドラインとします。
そこから社外依頼納期、社外提出納期、社内提出納期、社内確認納期など細かく余裕をもって納期を設定します。
全員が必ず納期を守ってくれればいいですが、そういう事ばかりではありません。
場合によっては成果物に不足があり、リテイクがかかる可能性があります。
余裕を持たせる依頼、確認体制を自分でコントロールすること、これが大事です。
おすすめ書籍
仕事は「段取りとスケジュール」で9割決まる! (アスカビジネス)
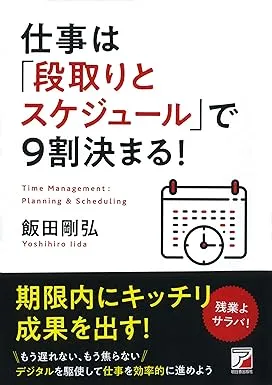
まとめ
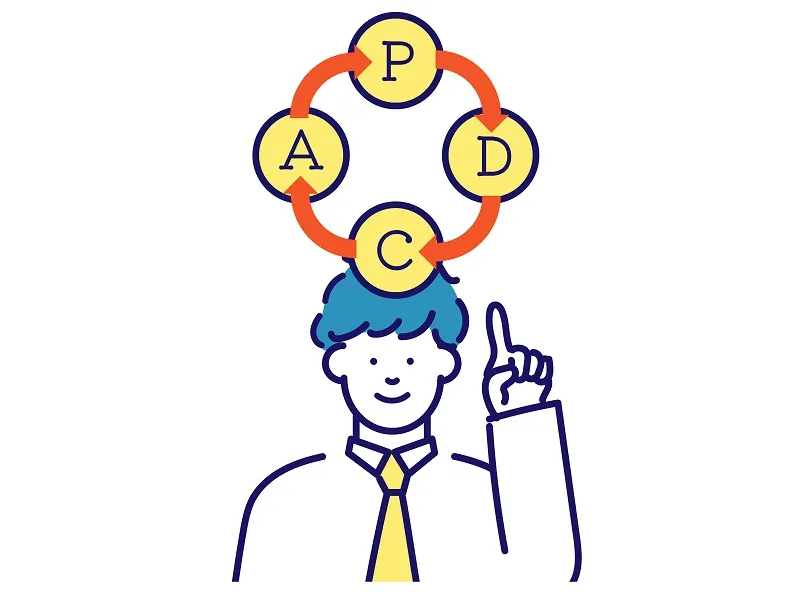
社会人に求められる能力を紹介しましたが、これらに関するもので何よりも大切なのは「行動力」です。
行動にうつせるか、うつせないかで変わります。
例え失敗したとしても、「やってみてできなかった」経験が増えます。
行動にうつさないとできるのかできないかもわからないままです。
真のコミュニケーション力、先読み姿勢、頭の回転の良さ、スケジュール管理力を身に着けたいのであれば、まずは実行しましょう。
最適解はあれど、正解がないからこそやり方は自分にしっくりくるものをチョイスする必要があります。
それを見つけるためにも、PDCAサイクルを回すのが大事です。
この記事を書いた人
『イートラスト株式会社 営業本部 / CSグループ』
2018年入社。和歌山県出身。食べることと料理がものすごく好き。七輪と石焼ビビンバ用の鍋etcを購入するもあまり使わず放置中。