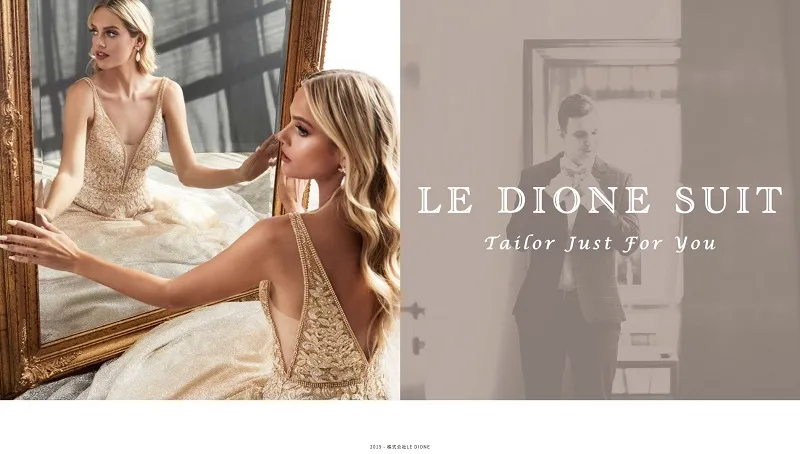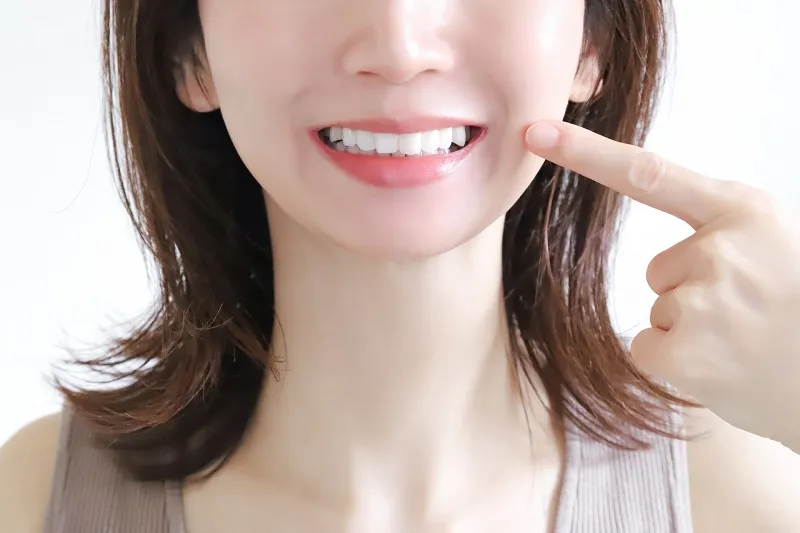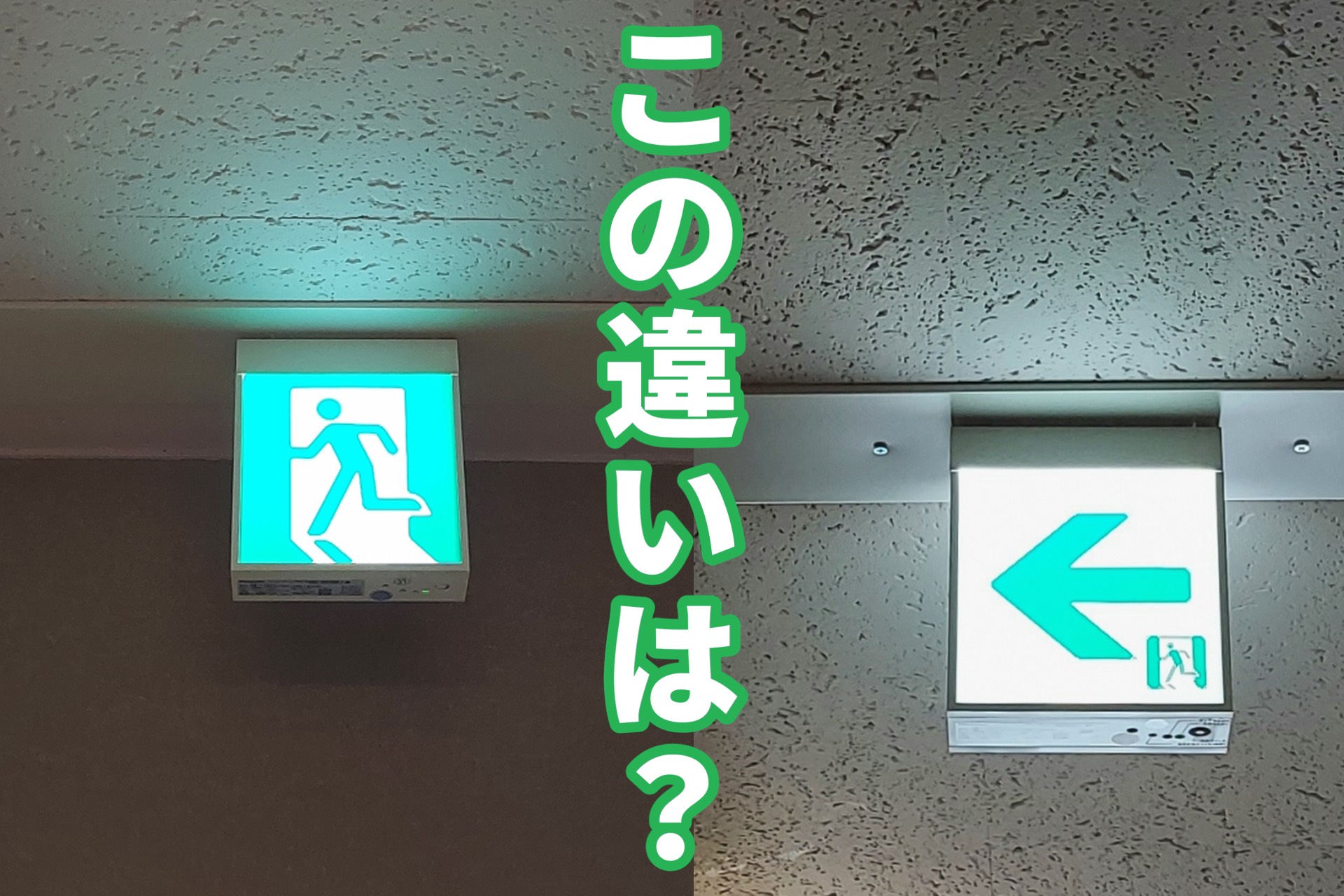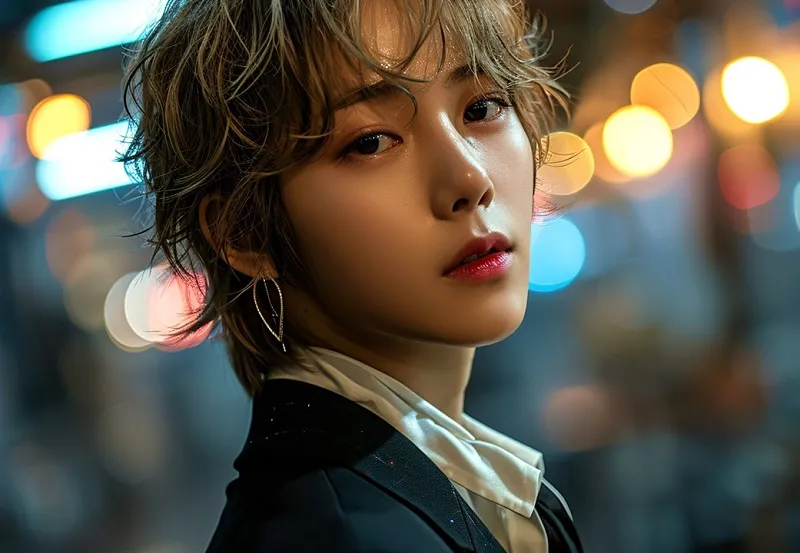2023 年 6 月 14 日公開
浴衣は昔、お風呂上りに着ていた?!

ここ数年各地で中止が続いていた夏祭り。
最近はコロナも落ち着いてきて、今年こそは浴衣を着てお祭りに行きたいという方も多いと思います。
しかし、そもそもなぜ夏に浴衣を着るようになったのでしょうか?
今回はその理由と、浴衣の歴史についてご紹介します。

歴史
浴衣の起源は奈良時代にまでさかのぼります。
語源は「 湯帷子(ゆかたびら) 」と言われており、当時は貴族が蒸し風呂でやけどを防ぐために着用していました。
鎌倉時代に現代同様裸で入浴するようになると、綿素材で汗を吸い風通しの良いことからお風呂上がりに着られるようになりました。
江戸時代になると銭湯が普及し、庶民の間でも浴衣が広まっていきました。当時は素材の通気性や吸収性を生かし、就寝時に寝間着として用いられるようになりました。
明治時代に入り洋服が広まると、日常的に着物や浴衣を着る人は減っていきました。
最近では、夏の風物詩として花火大会やお祭りに着る方が多いですよね。

なぜ夏に浴衣を着るの?
先程ご紹介したように、最初は貴族の間で着られていた浴衣は、そのうち庶民に広がっていきました。
その時は、下着のように汗ばむ体を拭くために着用していましたが、浴衣の生地も麻から木綿に変わるとそのまま外に出歩くようになったそうです。
桃山時代になると、いつの間にか浴衣はお祭りや盆踊り、花火大会でも着ることが流行りました。
これが、現代の夏祭りで浴衣を着ることにつながっているんですね!
まとめ
お祭りに着ることでより一層気分が上がる浴衣ですが、もともとはお風呂上りにパジャマとして着られていたんですね。
このように用途が変化して今の浴衣があると考えると、趣があっていいですよね。
今年の夏祭りはぜひ、浴衣を着てみてはいかがでしょうか?