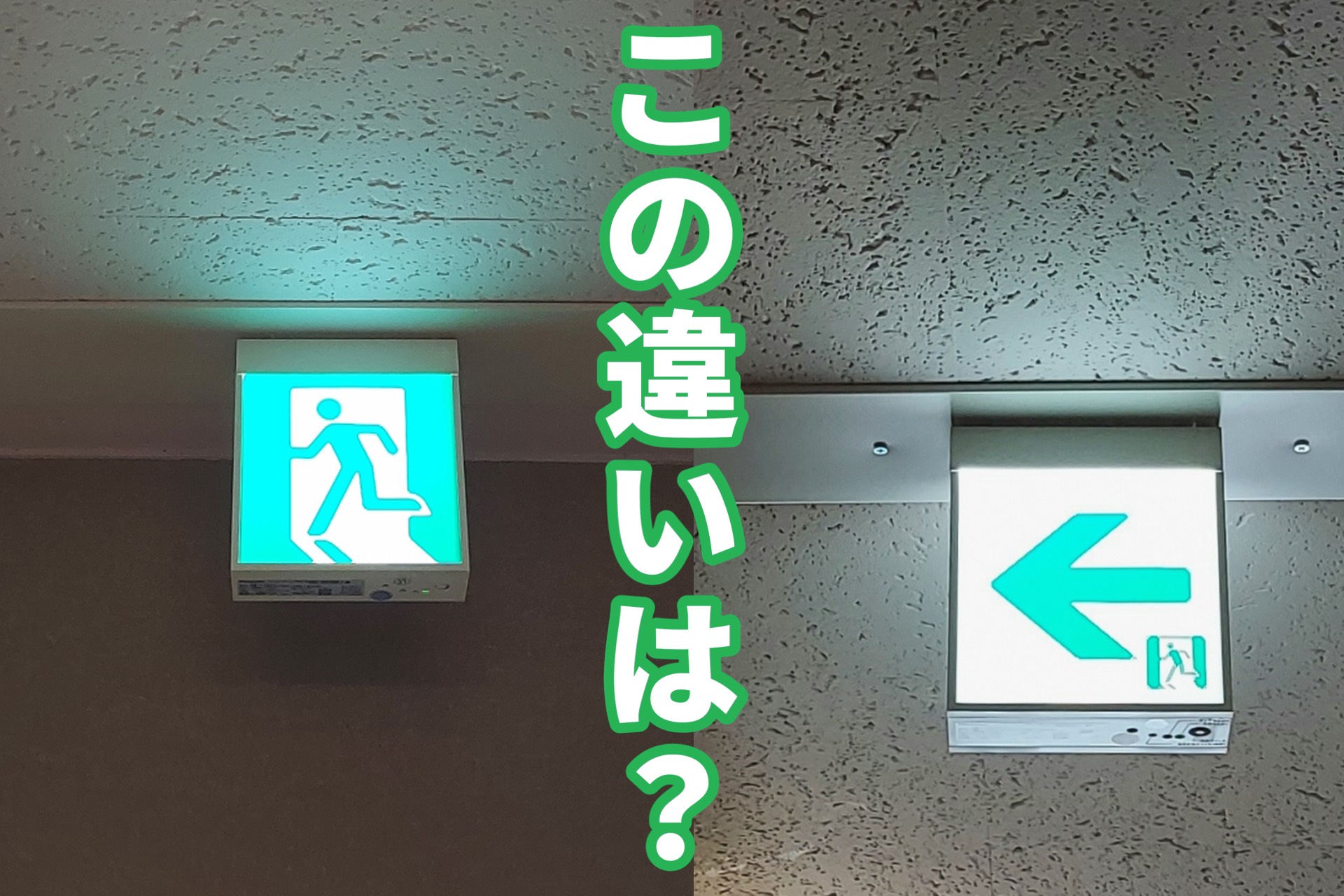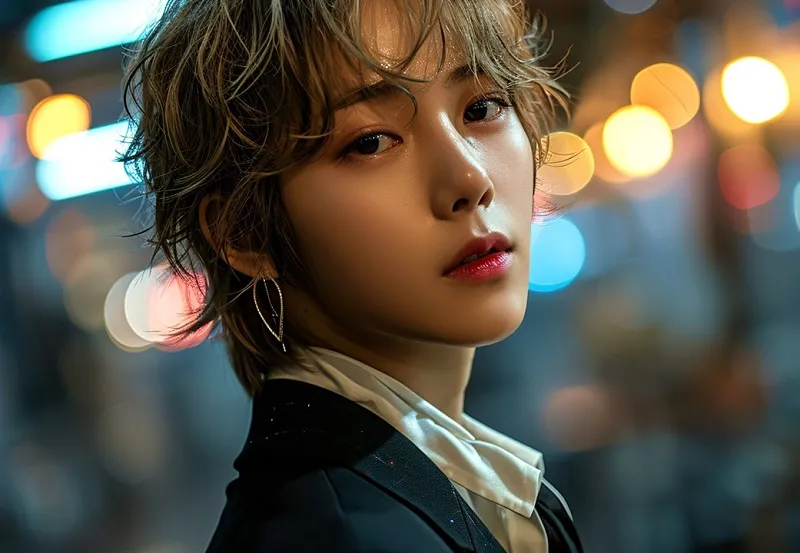2020 年 12 月 24 日公開
意外に知らない年賀状マナー! やりがちな「NG表現」は?

今年も年賀状の準備をしなければいけない時期になってきましたね。
皆様は年賀状を送りますか?
最近はLINEやSNSで新年の挨拶を済ます方も大勢いらっしゃって、年賀状を送らない人も増えているようです。
日本の郵便行政における年賀葉書の発行は戦後、1949年発行・1950年用のものが初めてで(年賀郵便用の年賀切手は戦前から発行されていた)、その当時の発行部数は1億8000万枚。以降日本の経済復興、人口の増加に伴い枚数を漸増させながら、1964年には10億枚、1973年には20億枚を超えたそうです
。これまでのピークは2003年の44億5936万枚。2008年以降は毎年減少傾向にあるようです。
今年は8月31日に日本郵便が、2021年用年賀ハガキの当初の発行枚数を19億4198万枚と発表。
2020年用年賀ハガキの発行枚数が23億5000万枚だったので、今年も発行枚数は減少傾向です。
とはいえ、年賀状はもらうとなんだか嬉しいですよね!?
そんな年賀状の意外にも知らないマナーをご紹介致します。
今回は年賀状の「賀詞」の種類・意味を知り、正しい使い方やマナーを押さえていきましょう。
「賀詞」とはお祝いの言葉のことを指します。
「寿」のような一文字、「迎春」のような二文字、「謹賀新年」のような四文字、また「明けましておめでとうございます」のような文章の賀詞があります。
このように年賀状の賀詞の種類は何種類かありますが、目上の方へ送る際はどの賀詞を選べばいいのでしょうか?
あまり、考えすぎても堅苦しい年賀状になってしまいそうですが、最低限のマナーは知っておいた方がよいでしょう。
◆相手が目上の方へ送る場合の賀詞
・「謹賀新年」「恭賀新年」など4文字の賀詞
・謹んで新年のお慶びを申し上げます
・謹んで初春のお慶びを申し上げます
・謹んで新春のご祝詞を申し上げます
◆目上の方へ送ってはいけない賀詞
・「寿」「福」など1文字の賀詞
・「賀正」「迎春」など2文字の賀詞
◆相手を選ばずに用いられる賀詞"
・明けましておめでとうございます
・新年おめでとうございます
・新春のお慶びを申し上げます
・Happy New Year
まとめて印刷会社などに年賀状の依頼を出す場合、相手ごとに年賀状のパターンを印刷することは難しいかもしれません。そのような場合には相手を選ばず使える賀詞を用いた年賀状を作るといいのではないでしょうか?
また、文章の重複もよくやってしまう間違いですので、気を付けましょう。
よくありがちなのが、「迎春」「謹賀新年」などの短い賀詞と「明けましておめでとうございます」などの文章の賀詞を重複して使ってしまうこと。賀詞を使ったら、添え書き(「今年もよろしく」などの文)には賀詞を書かないように注意しましょう。
今年は新型コロナウイルスの影響でなかなか直接会って、年末年始の挨拶が出来る機会がなさそうですので、年賀状を送ってみてはいかがでしょう?
最近はスマートフォンのアプリで簡単に作れたりするものもあったり、一つ一つ愛情を込めて手書きで作ってみたり、印刷業者さんにクオリティの高い年賀状を依頼したり、いろいろな選択肢から選べそうですね
。この記事を書いた人
『イートラスト株式会社 テクニカルチーム 主任/ B-rise運営事務局 副局長』
飲食業界で現場・SV・マーケティングを経験し、2014年イートラスト株式会社へ入社。ディレクター業務・カスタマーサポート業務を経て、現在はSEOやホームページ運用全般を請け負う「テクニカルチーム」を立ち上げ、責任者を担う。飲食業界に携わっていたこともあり、サービス業様へのWebマーケティング・SEO/MEOで貢献していくため、日々新しい試みを模索している最中です。